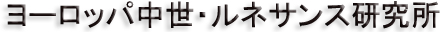ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第四回研究会報告
 2010年6月12日「ルネサンス精神をめぐって」と題して、早稲田大学で
2010年6月12日「ルネサンス精神をめぐって」と題して、早稲田大学で第四回研究会が開催されました。
プログラムは以下の通りです。
(それぞれのお名前は報告要旨記事にリンクしています。)
司会
根占献一(学習院女子大学教授)
報告
高橋朋子(早稲田大学非常勤講師)
「写実と肖似性 ーイザベラ・デステの肖像画をめぐって」
大川なつか(白鴎大学・立正大学非常勤講師)
「ジョン・コレットとヒューマニズム」
柳沼正広(創価大学非常勤インストラクター)
「エラスムスと異教古典―『反蛮族論』を手がかりに」
高橋氏は、イザベラ・デステの書簡や婚礼の際のコインなどから実像を推測しつつ、レオナルドの素描、フランチァからティツィアーノの肖像画に至るまでの制作の経緯を詳細に検討されました。そして、当時において写実とは、肖似性の高さではなく、まるで生きているかのような迫真性を意味したのではないかと指摘されました。絵画のイリュージョニスムを駆使した肖像画を描かせることで、「美しい女性」としての自身を獲得したイザベラの意図が明らかになりました。

大川氏は、イギリスにおける先駆的な人文主義者の一人であり、ヒューマニズム教育の雛形となった聖パウロ学校の設立者、ジョン・コレットの生涯を辿りながら、その思想を考察されました。フィレンツェの人文主義の影響を受けた新しい聖書研究と、友人エラスムスの助力を得て実践した教育の中に、コレットのキリスト教的ヒューマニズムの特質を見ることができました。

柳沼氏は、エラスムスの最初期の著作の一つであり、紆余曲折を経て出版された『反蛮族論』を詳細に分析されました。エラスムスは異教の古典の諸学問を擁護する論拠として、ヒエロニュムスを引用しましたが、その仕方は、異教学問に対して肯定・否定の両方の立場を論じたグラティアヌスに対して、肯定的な言葉だけを選んだばかりか、グラティアヌスもヒエロニュムスに基づいていることを伏せて論じるようなものであったことが指摘されました。

それぞれのご報告の要旨は後日改めて掲載いたします。
先回に引き続き盛況でありましたことをご報告するとともに、 足をお運びくださいました方々に、改めて深く御礼申し上げます。 (文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample