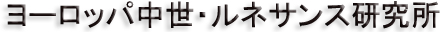ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第一回シンポジウム
2010年9月25日に早稲田大学にて当研究所の第一回シンポジウムが開催されました。 プログラムは以下の通りです。
全体のテーマ:「中世の時間意識」
司会 甚野尚志(早稲田大学文学学術院)
趣旨説明 益田朋幸(早稲田大学文学学術院)
報告(それぞれのお名前は報告要旨記事にリンクしています)
辻 成史(大阪大学名誉教授)
「語られる時間から内的表象の時間に」
佐野みどり(学習院大学教授)
「二重の時間、二重の空間―中世掛幅縁起絵の構造―」
堀越宏一(東洋大学教授)
「中世ヨーロッパの写本挿絵における時代表現と写実性」
辻氏は、ローマ帝国アウグストゥス帝時代のボスコトレカーゼの別荘を飾る「アンドロメダとペルセウス」、対作品の「ポリフェモスとガラテア」の二点の壁画を中心に、方形画面に描かれた物語の説話性と神話的風景の中に見る聖地や物語の主題を想起させるモティーフ、さらには明暗や人物像の象徴的な表現が、物語の経過を追うばかりではなく、ビザンティン時代にも連綿と連なるイコン的とも言うべき新たな宗教的感情を反映することを示唆されました。

佐野氏は、『志度寺縁起』『温泉寺縁起』、『観興寺縁起』といった13-14世紀の掛幅縁起絵の大画面を、地理的整合性と物語の逐次性がどのように積み重ねられているのかを実景を交えて読み解かれました。創建時の説話に登場する人物ばかりか当時の参詣者も詳細に描きこまれ、あたかも観覧者が神木や蘇生物語といった霊異譚を体感できるかのような重層的な構造、すなわち創建時と現在という二重の時間構造を鮮やかに分析されました。
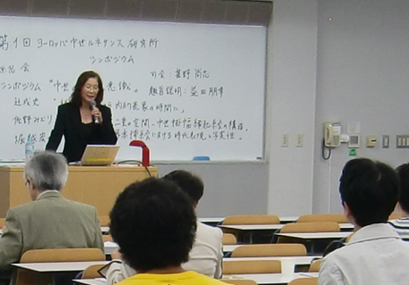
堀越氏は、歴史学の立場から中世写本挿絵を資料として捉え、描かれた事物が機能的に使われているかどうかという実証主義的な正確さにその写実性を見る、という方法論をご紹介くださいました。歴史画や挿絵を時代考証の可能性という視点で分析し、バイユーのタピスリーの囲壁都市や騎馬弓兵、クレシーの戦い(1346年)の両軍で使用された弓の差異を例に、同時代の事物描写の再現性の高さを考察されました。

三方による報告ののち質疑応答が行われました。 美術史、歴史学、そして洋の東西を越えた報告会は多いに白熱し、時間は飛ぶように過ぎました。 参加者は学生も多く、研究会に引き続き盛況でありましたことをまずはご報告いたします。

足をお運びくださいました方々に、改めて深く御礼申し上げます。 (文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample