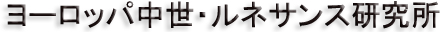ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第四回シンポジウム
去る2013年9月21日(土)に当研究所の第四回シンポジウムが開催されました。
プログラムは以下の通りです。
全体のテーマ:「中世地中海世界における翻訳と文化の伝承」
司会:甚野尚志(早稲田大学文学学術院教授)
報告:
高橋英海 (東京大学大学院准教授) (PDF版))
「ギリシア語からシリア語、アラビア語への翻訳―誰が何をなぜ翻訳したのか」
岩波敦子(慶応義塾大学教授) (PDF版)
「地中海からピレネーを越えて 中世ヨーロッパの自然科学 知の受容と伝播」
山本芳久(東京大学大学院准教授) (PDF版)
「トマス・アクィナス『対異教徒大全』の意図と構造」
コメント:村上寛(早稲田大学文学学術院助手)

高橋氏は、古代末期以降、地中海地域の文化がギリシア語からシリア語、アラビア語に翻訳され中央アジアや中国にまで伝播してゆく過程を、背景の総合的な分析と具体的な史料で詳細に紹介された。シリア語は、古代のアラム語の末裔としてローマ帝国からペルシア帝国に学問を伝え、支配側のギリシア語との共存し、キリスト教言語として宗教書の翻訳を行なわれた背景を持つ。最初期の翻訳では格言や文法や農学、博物誌などの実用書が残り、学校での教科書や修道士のための著作では、知名度の低い固有名詞や異教的要素が削除されるなどの変更が加えられた。哲学書や医学書には6世紀半ばの翻訳や注解書が残り、8世紀にはシリア語を介したアラビア語への翻訳の痕跡も残る。たとえば、ガレノスの医学書を訳したセルギオスは翻訳書の献呈相手への書簡で学知の起源としてのアリストテレスを紹介している。7-8世紀、天文学や論理学などを翻訳していた修道院ではそれらの学問の起源がバビロニアであるという書簡が残されている。また、8世紀末にギリシア語からアラビア語への翻訳を依頼されたネストリウス派の人物が、正教徒や他派の修道院に対しても慎重に立ちまわりつつ書物を探してほしいと書簡に記しており、宗派を超えて各翻訳書が広まっていることが伺える。ギリシア語からアラビア語への翻訳はキンディーやフナインらを中心とする翻訳サークルが知られ、9世紀のバグダードではアリストテレス学派が形成されるほど盛んであった。翻訳の動機は宗教論争や言語、神学論との関係も考慮されるが、高橋氏はたとえばシリア語であればウマイヤ朝の官僚機構においてのシリア語キリスト教徒の役割をも視野に入れ、広く研究すべきだろうと提案された。(文責 毛塚)

岩波氏は、中世地中海世界から北ヨーロッパへと至る自然科学知の継受の問題を、内容においてよりもむしろ、諸テクストの伝播という観点から考察された。古代ギリシアからアラビア世界を経由してヨーロッパに到達した自由四科、算術、幾何学、天文学、音楽は、その翻訳の過程において、伝説や通俗的な説明とは異なり、漸次的に社会内部へと浸透していったと考えられる。しかもその道筋や進度は不均一であって、必ずしもオリジナルのテクストが伝来するわけではなく、加筆・翻案やコンピレーションの末に断片的な伝達が行われてきた。伝播経路を史料に基づいて確定することは容易ではないが、天文学のようにテクストがアストロラーベ、天球儀といった最新の器具の導入とリンクした形で伝わっている点は見逃せない。インド・アラビア数字の原型であるGhubar記号は、まずアバクス表と呼ばれる計算表に、次いで偽ボエティウス文書において幾何学と融合するかたちでテクスト内に現れるといった複雑な経緯をたどって、11世紀前半から複数の経路を経て普及し、「12世紀ルネサンス」の知的基礎を形成することとなった。インド・アラビア式計算法にしても、アラビア数字ではなくローマ数字を用いて説明している、過渡的段階を示唆するテクストが現存していることは注目すべき点である。エウクレイデスの『原論』についても、一般的なイメージとは違って、ギリシア語写本からの翻訳よりもアラビア語経由での翻訳の方がよりオリジナルに近い構成を保っているという点が指摘され、テクスト伝播の複雑さの証左となっている。もちろん、いわゆるトレドのような知的拠点の存在は無視できないが、翻訳活動は体系的なプログラム、計画に基づいて一気呵成に行われたのではなく、個々のテクストの伝来状況または個人の関心に応じてなされたと考えるべきであろう。最後に氏は、時間の都合上、本報告では十分な説明ができないことを断りつつも、イングランドの学識者による知的受容の過程を理解することが、この問題を理解するうえで大きな意味を持つことを述べられ、今後の議論の方向性に関して貴重な一石を投じられた。(文責 鈴木)
山本氏は、トマス・アクィナスの『対異教徒大全』を詳細に分析され、その執筆意図とグレコ・アラブ的な知的伝統の受容の形態とを明らかにされた。同著のイスラーム批判は部分的、表層的なものにすぎず、神の完全性や被造物の秩序などの哲学的命題を人間生来の自然的な理性(自然理性)によって論じられるかについて多く紙数が割かれている。たとえば至福について、トマスは神を直接に観る至福直観こそが人間の究極目的であるとし、富・名誉・快楽など諸事物に在る幸福を次々と否定し、人間の究極的な幸福はこの世に存在せず、被造物は神を本質的に観ることはできない、とした。この論考の基盤となるアリテレスの幸福論と知性論はアラブ世界でも継承されたが、トマスはアヴェロエスらの知性の解釈を弁証法的に吟味しながら反証しつつ、換骨奪胎して自論を再構築している。さらに「この世の後に人間が不可死の仕方で存在して真の幸福に達することができる」ことを「措定する」というアリストテレス哲学の方法論で「理性」と「信仰」とを対置させ、人間が幸福に到達しうる唯一の論理的な帰結として聖書の言葉を提示している。トマスはキリストの受肉を理性的に考え神学の学問体系に組み込ませ、神的本性と人間本性が一致する出来事の雛型として、人間存在に希望を与える点にキリストの存在意義をとらえた。それによって超自然や啓示によらない「自然理性」という神学的な議論の新機軸を確立したのである。このように同著はグレコ・アラブの異教世界を中心に展開してきた知的伝統を継承し批判を加えて受容しながら、キリスト教的な真理を再構築する試みとして解釈できる。(文責 毛塚)

シンポジウムの質疑応答においても活発な議論がなされたこともご報告し、ご参加くださった皆様に改めまして感謝申し上げます。
Designed by CSS.Design Sample