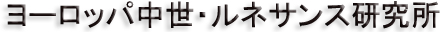ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第二十二回研究会報告
去る2016年11月5日(土)早稲田大学において第二十二回研究会が開催されました。
「早稲田大学高等研究所セミナーシリーズ〈新しい世界史像の可能性〉」との共催でした。
プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
お名前隣のPDF版のテキストリンクに要旨記事を掲載しております。
共通のテーマ「知の集積、発信拠点としての近世スイス」
報告(1)
雪嶋宏一(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)報告要旨(pdf)
「書誌学の源泉、コンラート・ゲスナー『万有書誌』」
報告(2)
パトリック・ シュウェマー(上智大学・学振研究員PD)報告要旨(pdf)
「ツヴィングリの和訳聖書」


雪嶋氏はコンラート・ゲスナー(1516-1565)の代表的な著作『万有書誌』(1545)を詳細に分析された。同書の項目や著者名数を改めて細かく算出され、図書館の蔵書目録との関連性をも指摘された。同氏はまた、版の比較から従来の増補訂正に加えて新たな差替え箇所を発見された。古今東西、多岐にわたる分野の著者情報がヨーロッパ各地の図書館から集められたが、その情報源はトリテミウス(1462-1516)の著者目録(1494、1531)や16世紀の印刷業者マヌーツィオらの印刷版売書目録(1534)など、同時代の著者や印刷業者にも及んだ。ゲスナーは同書において、中世的な著者中心の目録から、著作を主体とする印刷本の書誌記述要素を確立し、近代書誌学の礎を生み出したと結論される。

シュウェマー氏はヴァチカン図書館所蔵のバレト写本(Reg.lat.459)の福音書朗読集の邦訳された文体を詳細に分析された。同写本は1591年頃ポルトガル人イエズス会士バレト(1564-1620)によって日本語学習のためにローマ字で奇跡譚、受難物語、聖人伝などが書写されたものである。その福音書朗読集は、当時流布していたラテン語聖書と、ツヴィングリの弟子によって編まれたチューリヒ版ラテン語聖書を並べて、日本宣教活動の熱心な貢献者でもあったフェリペ2世の勅許のもとで印刷された『双訳聖書』(サラマンカ版)を原本としたということを、同氏が指摘した。翻訳の際には、2種類の本文を適宜選択しながら、逐語訳を避け、より自然な日本語になるよう試みられた。とくに幸若舞の修辞法を模倣している点が着目される。一方、その文面には漢文の訓読法にラテン語文法を合わせた、同氏が「羅文訓読」と呼ぶ独自の訓釈法が見られる。同氏はこの翻訳と訓読という二つの言語体系を併せ持つ同写本の世界史的な意義を指摘された。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。 お運びくださった皆様、ありがとうございました。

(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample