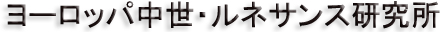ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第六回シンポジウム報告
去る9月19日(土)に早稲田大学において当研究所の第六回シンポジウムが開催されました。
早稲田大学人文科学研究センター・研究部門「ヨーロッパ基層文化の学際的研究」との共催でした。
 プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。お名前からはテキスト記事、()内からはPDF版の要旨記事にリンクを張っております。
早稲田大学ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所第六回シンポジウム
日時:2015年9月19日(土)14時~18時
場所:早稲田大学戸山キャンパス39号館2階2219教室(美術史実習室)
タイトル:「中世ヨーロッパの写本とキリスト教文化」
司会:甚野尚志(早稲田大学教授)
報告(1)「旧約聖書写本挿絵-預言書と八大書写本を中心に」(PDF版) 瀧口美香(明治大学准教授)
報告(2)「「中世ラテン語 ≪ remicha ≫ をめぐって」(PDF版) 西間木真(早稲田大学ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所招聘研究員)
報告(3) 「ナジアンゾスのグレゴリオスはどう受容されたか-中世ロシア写本におけるテクストの継承と変容」 (PDF版) 三浦清美(電気通信大学教授)
コメント:益田朋幸(早稲田大学教授)
報告:

瀧口氏は、10世紀半ばから13世紀にかけて制作された現存するビザンティンの旧約聖書写本挿絵、とりわけ、特徴的な発展を遂げた八大書と預言書写本を中心に紹介された。ヴァイツマンとラウデンという写本挿絵研究の二大潮流の研究手法を踏まえながら、預言者の描き分け、背景描写、擬人像に関するギリシア語表題分析、末尾を飾るルツ記の図像解釈など、多角的かつ大胆な検討をなされた。
西間木氏は、11世紀から12世紀のフランスの音楽理論に関する諸写本を調査されるなかで、現在、パリの国立図書館に所蔵されている写本に、これまで知られていなかったラテン語を確認した。今回の報告では当時の音楽理論との関わりからその語の意味を推定された。


三浦氏は、14世紀から17世紀の5点の中世ロシア写本に残る説教集、とりわけ著名な教父ナジアンゾスのグレゴリオスに帰せられながら、ギリシア語からの翻訳の際、大きく改変され、原典テクストが反映されていないと評される作例を詳細に検討された。その結果、異教風俗の論難という主眼や、論術方法など原典と多くの共通点が見いだされ、説教集のテキストは形を変えながらもグレゴリオスの精神を着実に受容していたことが明らかになった。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも記して感謝申し上げます。 お運びくださった皆様、ありがとうございました。

(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample