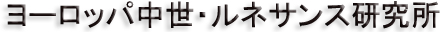ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第六回研究会報告
去る4月9日、「ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所」第六回研究会が 早稲田大学にて開催されました。 全体のテーマは「中世の写本をめぐって」でした。 プログラムは以下のとおりです。 (それぞれのお名前は報告要旨記事にリンクしています。)()内はPDF版です。
報告
西間木 真 (ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所招聘研究員)
アキテーヌ写本( BnFlat.1118) を通してみたロマネスク音楽の諸問題(PDF版)
辻 絵理子(早稲田大学文学学術院)
「ストゥディオス修道院写本工房の磔刑図像―礼拝する人物と犠牲の仔羊」(PDF版)

西間木氏は音楽写本研究の立場から、11世紀までの世俗音楽写本を、南フランスのサン・マルシャル修道院に由来するアキテーヌ写本(BnF, lat.1118) を通して詳細に紹介された。まず多岐にわたる音楽写本研究の背景と現状を説明され、楽譜形式が成立する12世紀以前に、カロリング期に遡る音楽写本伝統を土台として新たに制作された南フランスの特徴的な記譜法を見た。具体的には各旋法ごとの譜面の読み方を、実際の使用法、歌詞と旋律の表記、用語の定義などを写本作例に沿って詳細に辿った。アキテーヌ写本にまとめられた5種類の写本は、歴史記録、挿絵などから推測される制作年代の同定問題を皮切りに、現時点においてそれぞれに様々な見直しが必要である。氏はこの点から、音楽におけるロマネスクの呼称とその範疇の設定にも問題を提起された。
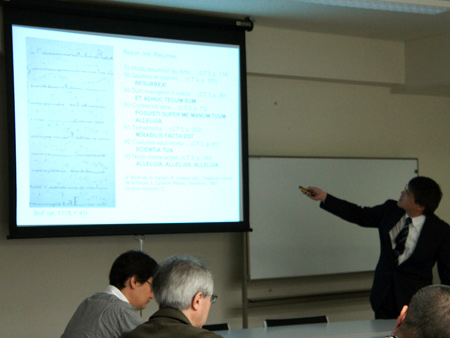
辻氏は、磔刑図像の現存作例を概観したのち、ストゥディオス修道院で制作された写本挿絵『パリ福音書』(Cod.Paris.gr.74)および『テオドロス詩篇』(B.L.,London,Add.19.352)における特徴的な磔刑図像を紹介した。同修道院の写本には聖書内容の逐語的な描写を始め、予型論、神学的な意味解釈が重層的に盛り込まれた多くの挿絵が残されている。氏は両写本に共通する「磔刑図像」のキリストの足元に描かれた礼拝する一対の人物に着目し、その図像はキリスト教図像の生成期である5世紀の作例に遡りうるもので、11世紀の同修道院写本工房においてそれまでと異なる文脈で採用され、それぞれの写本の中で他の挿絵と結びついて新たな意味を獲得したのではないかと結論した。

お運びくださった皆様、ありがとうございました。 盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。 (文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample