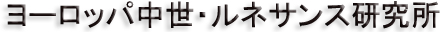ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第二十三回研究会報告
去る2017年6月24日(土)に早稲田大学において当研究所の第二十三回研究会が開催されました。
全体のテーマ「聖書解釈と信仰実践」でした。
プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
お名前隣のPDF版のテキストリンクに要旨記事を掲載しております。
報告(1)
毛塚実江子(共立女子大学非常勤講師)報告要旨(pdf)
「10世紀イベリア半島における写本挿絵の刷新と諸問題」
報告(2)
鈴木喜晴(早稲田大学本庄高等学院非常勤講師)報告要旨(pdf)
「14世紀後半における厳修化と反ー托鉢修道会」
毛塚氏は10世紀に大幅な刷新がみられたイベリア半島写本挿絵と、研究に伴う諸問題を取り上げながら、改革点を中心に写本制作の背景の解釈を試みた。当時の挿絵は図像の類似性から古代ローマやササン朝ペルシア、西ゴート、メロヴィング朝、カロリング朝からの伝統と、同時代のビザンティン、アル・アンダルスなど多様な影響関係の可能性が指摘されるも、それらから写本の構成や制作意図を再構築することは難しかった。しかし各写本の刷新点に着目するなら、黙示録註解写本であるベアトゥス本にダニエル書註解や福音書記者像等が取り入れられ、旧約・新約両聖書の関連性が重視される神学的な背景が想定される。同氏はこのような時代背景において大型新旧一巻本聖書である『960年聖書』が制作されたと指摘した。
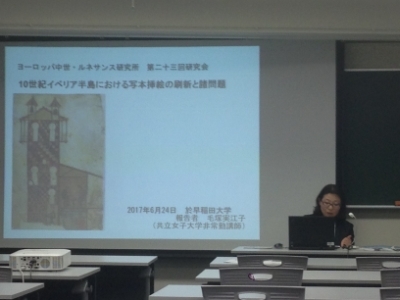
鈴木氏はジョン・フォックス(1516-1587)の著作『殉教者伝』(1563)の成立において、元カルメル会士ジョン・ベイルが果たした役割と、彼が参照した写本Bodley Ms. e Mus. 86の性格についての分析を行った。初期の宗教改革者たちがウィクリフとロラード派についての情報源として利用したこの写本は、本来は14世紀における清貧と托鉢修道会についての一連の論争をカルメル会が15世紀前半にまとめたものであり、ウィクリフとロラード派著作家たちも、本来は会に対する批判者の流れに連なる人々であった。だが、写本が一世紀のち、宗教改革の時代に参照されると、この文書は本来の文脈を離れ、改革の先駆者たちの言行を記録した「聖人伝」のコンテンツとして新たな意味を与えられた、と同氏は結論している。

盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。 お運びくださった皆様、ありがとうございました。

(文責:鈴木・毛塚)
Designed by CSS.Design Sample