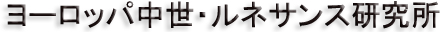ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第五回研究会報告
2010年11月6日、「ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所」第五回研究会が 早稲田大学にて開催されました。
全体のテーマは「テクストからの時間意識」でした。 プログラムは以下のとおりです。 (それぞれのお名前は報告要旨記事にリンクしています。)
報告
田島照久(早稲田大学文学学術院教授)
「「永遠の第一の単一なる今」-マイスター・エックハルトの時間論」
竹田千穂(早稲田大学大学院博士課程)
「歴史を物語ること-フロワサールの『年代記』第三巻「ベアルンの旅」のテクストにおける時間意識-」
鈴木 喜晴(早稲田大学大学院博士課程)
「Adhuc modernus puer es-カルメル会士ヨハネス・フォン・ヒルデスハイムの 修道制観と時間意識」
 田島氏は、中世末期の神秘思想家マイスター・エックハルトの時間論をテクストに側して紹介された。アウグスティヌスの時間論を継承する中世哲学において人間の精神にとっての時間は、過去も未来をも回収する「永遠の今」と捉えられ、あたかも中世絵画の上方に描きこまれる神の手が、説話場面の時間に同時に介入するように、神は、過去、現在、未来の三つの時間のいずれにも自由に介入する。エックハルトはこれに加え、『創世記』と『ヨハネによる福音書』の冒頭で語られる「始原」こそ、神の永遠の根拠であり、時間を超越すると同時に、独り子の受肉によって時間に介在し、救済史を在らしめるために絶え間なく働きかける存在であるとした。そこにおいて唯一であり同一であり単一である神の業、「永遠の今」が語られる。さらに「始原」とは『ヨハネ黙示録』で説かれる「終極」でもあり、はじまりの瞬間において完了し、同時に絶えず創造しつづけ、子を誕生せしめているのである。この「永遠の今」は時間として認識しうる現在ではなく、人間の理性的霊魂、「魂の根底」に神と神の神性とともにある。エックハルトの「魂の中における神の(子の)誕生」という教義はこれらの時間論の文脈で説かれるのである。
田島氏は、中世末期の神秘思想家マイスター・エックハルトの時間論をテクストに側して紹介された。アウグスティヌスの時間論を継承する中世哲学において人間の精神にとっての時間は、過去も未来をも回収する「永遠の今」と捉えられ、あたかも中世絵画の上方に描きこまれる神の手が、説話場面の時間に同時に介入するように、神は、過去、現在、未来の三つの時間のいずれにも自由に介入する。エックハルトはこれに加え、『創世記』と『ヨハネによる福音書』の冒頭で語られる「始原」こそ、神の永遠の根拠であり、時間を超越すると同時に、独り子の受肉によって時間に介在し、救済史を在らしめるために絶え間なく働きかける存在であるとした。そこにおいて唯一であり同一であり単一である神の業、「永遠の今」が語られる。さらに「始原」とは『ヨハネ黙示録』で説かれる「終極」でもあり、はじまりの瞬間において完了し、同時に絶えず創造しつづけ、子を誕生せしめているのである。この「永遠の今」は時間として認識しうる現在ではなく、人間の理性的霊魂、「魂の根底」に神と神の神性とともにある。エックハルトの「魂の中における神の(子の)誕生」という教義はこれらの時間論の文脈で説かれるのである。
 竹田氏は、ジャン・フロワサール(1337?-1404?)の著作『年代記』のテクストにおける時間意識の変遷を考察された。氏によれば『年代記』第三巻からフロワサールの執筆形式と著作態度はともに大きく変化するという。例えば第一巻の序文では武勲を語る重要性を長々と述べた後ようやく最後に名を名乗るのに対し、第三巻の序文では早々に作者として名乗りをあげる。またクロノロジックに三人称を用いて出来事を語っていく最初のニ巻に比べて、第三巻の「ベアルンの旅」と呼ばれる部分では、この地の領主フォワ伯を訪ねた旅の報告を対話体を用いて旅行記のような体裁をとって描き、話者と聞き手フロワサールが会話をかわす時間と、話者が物語る逸話の中を流れる時間のずれが生み出す効果を生かして、フォワ伯領内の禁忌の話題であったフォワ伯の子殺しまでも、脚色を加えながら物語り、そこで語られる時間を、読み手に共有させ、追体験させるような記述の工夫を試みているのである。
竹田氏は、ジャン・フロワサール(1337?-1404?)の著作『年代記』のテクストにおける時間意識の変遷を考察された。氏によれば『年代記』第三巻からフロワサールの執筆形式と著作態度はともに大きく変化するという。例えば第一巻の序文では武勲を語る重要性を長々と述べた後ようやく最後に名を名乗るのに対し、第三巻の序文では早々に作者として名乗りをあげる。またクロノロジックに三人称を用いて出来事を語っていく最初のニ巻に比べて、第三巻の「ベアルンの旅」と呼ばれる部分では、この地の領主フォワ伯を訪ねた旅の報告を対話体を用いて旅行記のような体裁をとって描き、話者と聞き手フロワサールが会話をかわす時間と、話者が物語る逸話の中を流れる時間のずれが生み出す効果を生かして、フォワ伯領内の禁忌の話題であったフォワ伯の子殺しまでも、脚色を加えながら物語り、そこで語られる時間を、読み手に共有させ、追体験させるような記述の工夫を試みているのである。
 鈴木氏は、ヨハネス・フォン・ヒルデスハイム(1310/20-1375)の著作から、カルメル会の時間意識を明らかにされた。カルメル会は13世紀後半、托鉢修道会として認可されたが、その起源の古さを旧約聖書に求めたために批判を受けた。ヒルデスハイムの『擁護者と誹謗者の対話』では、ドミニコ会と想定される誹謗者と、会の権威や会則の正統性についての議論が行われている。1324、27年にはカルメル山の隠修士の後継者が、キリストの受肉後に聖母を記念して「教会」を建てたことにちなみ「カルメル山の聖母マリアの兄弟修道会」とした。これらの会史は繰り返し主張され、ロレンツェッティによる同会のための『シエナの祭壇画』においてもエリヤに従うカルメル山麓の隠修士らや、修道会則を与えたエルサレム総大司教アルベルトをはじめ、教皇達によって会則や権威を認められる場面が描かれた。このように、カルメル会は同時代の批判を受けながらも、聖書註釈や歴史著作、教会法などを駆使し、旧約聖書に連なる独自の歴史観を掲げていたのである。
鈴木氏は、ヨハネス・フォン・ヒルデスハイム(1310/20-1375)の著作から、カルメル会の時間意識を明らかにされた。カルメル会は13世紀後半、托鉢修道会として認可されたが、その起源の古さを旧約聖書に求めたために批判を受けた。ヒルデスハイムの『擁護者と誹謗者の対話』では、ドミニコ会と想定される誹謗者と、会の権威や会則の正統性についての議論が行われている。1324、27年にはカルメル山の隠修士の後継者が、キリストの受肉後に聖母を記念して「教会」を建てたことにちなみ「カルメル山の聖母マリアの兄弟修道会」とした。これらの会史は繰り返し主張され、ロレンツェッティによる同会のための『シエナの祭壇画』においてもエリヤに従うカルメル山麓の隠修士らや、修道会則を与えたエルサレム総大司教アルベルトをはじめ、教皇達によって会則や権威を認められる場面が描かれた。このように、カルメル会は同時代の批判を受けながらも、聖書註釈や歴史著作、教会法などを駆使し、旧約聖書に連なる独自の歴史観を掲げていたのである。
 お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、質疑応答では活発な議論がなされたことをあわせて報告いたします。
(文責:毛塚)
お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、質疑応答では活発な議論がなされたことをあわせて報告いたします。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample