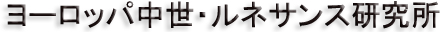ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第十二回研究会報告
去る4月20日に早稲田大学にて当研究所の第十二回研究会が開催されました。
プログラムは以下の通りです。
それぞれの報告者のお名前は要旨記事にリンクしています。
全体のテーマ:「リヴァイヴァル―ヨーロッパ文化における再生と革新」
報告者:
「後期ビザンティン聖堂(13~15C)におけるプラティテラ型聖母子像」
菅原裕文(早稲田大学非常勤講師) (PDF版)
「写本学 (codicologie)とリヴァイヴァル」
西間木真(ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所招聘研究員)(PDF版)

 菅原氏は、小アジア、キプロス、バルカン南部に及ぶご自身のフィールドワークを映像資料によって紹介しつつ、13世紀から15世紀にかけて同地域の主に小聖堂において、アプシス装飾に「プラティテラ型」と呼ばれる聖母子像の類型が顕著に増加することを指摘した。ビザンティンにおけるアプシス装飾では、初期の顕現図像から中期以降の聖母子像への変遷が認められるが、これにはイコノクラスム期に聖像の製作が神の受肉の証として擁護されたため、旧約的な再臨の主題が後退した影響を指摘しうる。とりわけプラティテラ型聖母子像では、オランスの姿勢で描かれ寄進者への加護を含意するプラケルニティッサ型の聖母に、インマヌイルが重なるかたちでしばしば正面のメダイヨン内に配置され、受肉の含意が強調されている。受肉の含意はアカティストス讃歌第3連を想起させる銘文が添えられている作例からも裏付けられる。加えて左右に吊り香炉を持って控える大天使を伴うパターンも存在し、プラティテラ型聖母子像はいわばモティーフの「オール・イン・ワン」的な様相を呈している。これは後期ビザンティンにおいて、小規模な寄進による聖堂の小型化と同時に、十二大祭サイクルに連続説話サイクルを加え、新たな図像が挿入されるような、装飾プログラムの多層化、複雑化という矛盾した傾向が進行しており、この状況において小さな壁面に可能な限り多くの情報を盛り込む手法が要求された結果であると考えられる。
菅原氏は、小アジア、キプロス、バルカン南部に及ぶご自身のフィールドワークを映像資料によって紹介しつつ、13世紀から15世紀にかけて同地域の主に小聖堂において、アプシス装飾に「プラティテラ型」と呼ばれる聖母子像の類型が顕著に増加することを指摘した。ビザンティンにおけるアプシス装飾では、初期の顕現図像から中期以降の聖母子像への変遷が認められるが、これにはイコノクラスム期に聖像の製作が神の受肉の証として擁護されたため、旧約的な再臨の主題が後退した影響を指摘しうる。とりわけプラティテラ型聖母子像では、オランスの姿勢で描かれ寄進者への加護を含意するプラケルニティッサ型の聖母に、インマヌイルが重なるかたちでしばしば正面のメダイヨン内に配置され、受肉の含意が強調されている。受肉の含意はアカティストス讃歌第3連を想起させる銘文が添えられている作例からも裏付けられる。加えて左右に吊り香炉を持って控える大天使を伴うパターンも存在し、プラティテラ型聖母子像はいわばモティーフの「オール・イン・ワン」的な様相を呈している。これは後期ビザンティンにおいて、小規模な寄進による聖堂の小型化と同時に、十二大祭サイクルに連続説話サイクルを加え、新たな図像が挿入されるような、装飾プログラムの多層化、複雑化という矛盾した傾向が進行しており、この状況において小さな壁面に可能な限り多くの情報を盛り込む手法が要求された結果であると考えられる。
西間木氏は、ヨーロッパにおける写本学の現状を、特に史料の喪失と復元への努力という観点から論じられた。戦災によって文書館が甚大な損害を被ったカンブレーやシャルトルでは、戦前に撮影されたマイクロフィルム、一部現存する被災史料などを駆使して回復への努力が現在も続けられている。宗教戦争、フランス革命、二度にわたる大戦によって大部分の写本を喪失したフランスでは決して容易なことではないが、各文書館所蔵資料の照会や市民の私的に所有する写本調査、上書きのため削られた写本への科学的アプローチ、革命以前の写本リスト調査、写本断片の復元など、多くの手段を組み合わせることで、一定の成果が上がっている。氏は特に、自ら研究対象とされている写本BnF, lat.7211を例に挙げて写本学の可能性を示された。本写本は複数のlibellusを合本したものであり、それらはかつてリュクスイユにおいて作成されたと言われていたが、今日では少なくとも一部は南西フランスにおいて書かれたことが判明している。にもかかわらず本写本とBnF, lat.7212の類似性をもとに、7212から7211へのコピーを推定したリュクスイユ起源説にはなお検討に値する部分が存在している。字体、内容の欠落、誤記、写本自体の綴じ込み形態などについての複合的な精査により、実は両写本が共に、現在では失われた未知の写本一部ないしは複数から生まれたコピーであることが判明した。写本学は現在知られていないものの再生を成し遂げるという点でまさにリヴァイヴァルの学問なのである。

お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
(文責:鈴木)
Designed by CSS.Design Sample