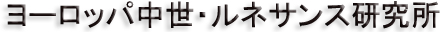ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第九回シンポジウム報告
去る2018年9月22日に早稲田大学において、当研究所の第九回シンポジウムが開催されました。
「早稲田大学高等研究所セミナーシリーズ〈新しい世界史像の可能性〉」との共催でした。

プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
お名前隣のPDF版のテキストリンクに要旨記事を掲載しております。
タイトル:「ルネサンス期ヨーロッパにおける魔女表象と社会の変容」
司会:高津秀之 (東京経済大学准教授)
報告1: 黒川正剛 (太成学院大学教授)
「変容する魔女表象―身体と感情をめぐって」報告要旨(pdf)
報告2: 田島篤史(大阪市立大学都市文化研究センター研究員)
「帝国都市ニュルンベルクの魔女裁判にみる悪魔学的要素と萌芽的近代性」報告要旨(pdf)
報告3: 小林繁子 (新潟大学准教授)
「名誉をめぐる攻防―「魔女」の名誉棄損訴訟と司法利用の戦略」報告要旨(pdf)

黒川氏は、魔女狩りが行われた15世紀から17世紀に制作され流布した魔女の図像を身体・感情表現を含む多義的な「表象」として詳細に分析された。魔女狩りが始まった1480-90年代に作成された木版画に描かれた魔術や変身を行う魔女の図像は、魔女のイメージの原型となり、16世紀前半にはデューラーやバルドゥングらの画家によっても引き継がれ、魔女のステレオタイプを形成していく。1560年代以降、魔女狩りが激化するとともに図像も増え、魔女に対する恐怖や嫌悪の感情が社会的に共有されていったと考えられる。版画、素描、絵画、とりわけ悪魔学書やビラなどの印刷物に挿絵として付され広まった魔女の図像は、文字が読めない人々にさえも魔女の実在を確信させるものであった。氏は、具体的な魔女の図像、箒と棒に跨がり空中飛行をしたり、雄山羊を崇拝したり、サバトに集まるといったステレオタイプの視覚イメージが当時の社会に与えた影響は、身体史や心性史、感情史の研究で語られるべきテーマであると指摘された。

田島氏は、魔女をめぐる「表象=悪魔学(書)」と「実践=魔女裁判」との関連について検討を加えられた。従来の歴史叙述では、15世紀後半の異端審問官H. インスティトーリスの『魔女への鉄槌』が、魔女のステレオタイプを確立し、魔女裁判の激化を引き起こしたと語られるが、氏は、悪魔学の隆盛と裁判の増加との間に単純な因果関係を設定することは実証的な根拠に欠けると指摘する。帝国都市ニュルンベルクでは『鉄槌』の製作年が魔女裁判の経過の重要な画期とは重ならず、むしろカロリーナの発布(1532年)を契機とした法と裁判手続きの近代化が重要視される。悪魔学書の影響は、判決に至る審理や自白の過程にまず現れ、次いで市参事会の発布した俗語の法令が印刷メディアを通じて広く周知されたことで、魔術的慣習が刑罰の対象となると認識され、民衆の魔女・魔術のイメージが変化していった。「表象」と「実践」との関係は、長期の、より複雑な社会の「近代化」過程において理解されなければならないと氏は結論する。

小林氏は、魔女中傷に対する名誉裁判訴訟を司法の利用という観点から検討された。魔女中傷に対しては慣習法に基づく簡易的裁判においても、比較的高額な罰金が中傷者に科せられていた。これに対し、学識法に則る名誉棄損訴訟は原告と被告双方に弁明の機会があり、賠償や刑罰が科される裁判制度であった。氏はこの制度が具体的にどのような利用をされていたか、17世紀の北西ドイツのヴェストファーレン公領の小貴族と裕福な農民との裁判記録をもとに詳細に分析された。事例では原告と被告双方の主張が応酬され、魔女犯罪の告発の他に、日常的な諍いや法廷外での衝突があり、被告は敗訴しながらも上告し続け、第三審の判決前に和解が成立していた。名誉棄損訴訟は、法の専門的知識を持つ弁護人の準備や証人への聴取など費用と時間を要するが、それを負担しうる人々にとっては、和解を含む主体的な解決を可能にする選択肢であり 、制度の複雑さ・未確立がそれを可能にしていたと指摘された。
報告後、会場からの質問を交えたディスカッションが行われました。

盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも記して感謝申し上げます。
お運びくださった皆様、ありがとうございました。
(文責:鈴木・毛塚)
Designed by CSS.Design Sample