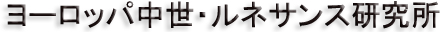ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第二回シンポジウム
2011年9月24日に早稲田大学にて当研究所の第二回シンポジウムが開催されました。 プログラムは以下の通りです。
それぞれのお名前は報告要旨にリンクしています。
全体のテーマ「リヴァイヴァル―ヨーロッパ文化における再生と革新」
報告
伊藤亜紀 (国際基督教大学)
「日常の美-「新版」アラビア医学書『タクイヌム・サニターティス』」(PDF版)
根占献一 (学習院女子大学)
「ローマ再生とエジディオ・ダ・ヴィテルボ」(PDF版)
佐藤真一 (国立音楽大学) 「「近代歴史学の父」ランケと中世研究」(PDF版)

伊藤氏は、14世紀から15世紀にかけてつくられた11世紀のアラビア医学書『タクイヌム・サニターティス』写本を紹介された。このラテン語写本には健康に関する様々な項目に沿って挿絵が加えられ、人物の服装描写に特徴が見出される。代表的な作例であるパリ国立図書館の写本(ms.nouv. acq.lat.1673)とウィーンのオーストリア国立図書館の写本(Codex Vindobonensis Series Nova 2644)を比較すると、前者には、時折庶民を戯画的にとらえる姿勢が感じられ、注文主である貴族が娘の嫁入り道具の一つとして同写本を制作させた経緯が想起される。後者は、服装による階級描写が目立ち、例えば見た目の美しい果樹と貴族の服装を組み合わせるなど、事物と関連させて描き分けがなされている。両者の挿絵は、細かい類似点を見せる一方で、身振りや構図などを大きく異にする作例もあり、ラテン語版写本の挿絵は挿絵師の裁量に任されていたのではないかと推測される。
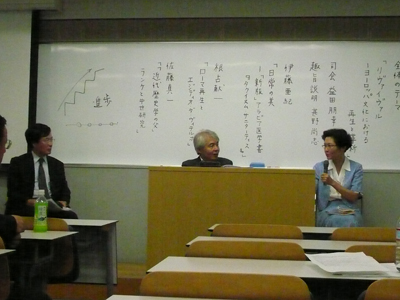
根占氏は16世紀を代表する雄弁家、神学者、思想家エジディオ・ダ・ヴィテルボ(1469-1532)を紹介された。エジディオはアウグスティヌス会の隠修士会総長を勤め、枢機卿を経てヴィテルボの司教となっている。その時代認識においてはプラトン主義と聖書的歴史観とが結び付けられ、エジディオは新世界にキリスト教が拡大する16世紀を「時代、人類、教義」の三つが充溢した史的頂点とした。1507年の説教演説では、人間の尊厳はキリストの受肉にあり、そこに神の愛と、それを体現する信仰の中心地としてのローマの尊厳と宿命を見出だしている。同説教はローマ市民のためにサンタゴスティーノ教会において俗語で繰り返された。また、ヤヌス神やエトルリア文明にも触れ、ユリウス2世とユリウス・カエサルとを比較するなど、古代とローマの精神とを積極的に融合した。彼の足跡には15世紀の人文主義者とは明らかに異なる、ルネサンス的なローマの再生が認められるだろう。
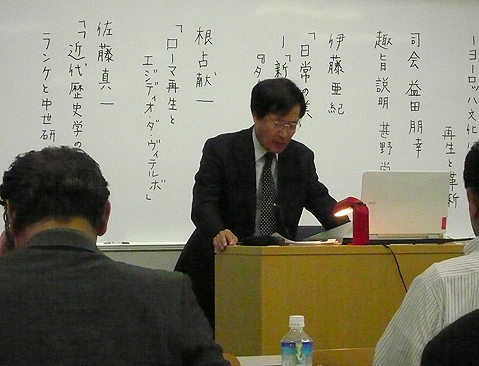
佐藤氏は、厳密な史料批判による近代歴史学を確立したレオポルト・フォン・ランケ(1795-1886)の中世研究を紹介された。ランケは18世紀的な進歩史観を批判し、各時代が「神に直接する」価値を持つとして、中世を暗黒時代と見なす考えを退けた(1854年)。1817年、ランケはヴュルツブルクの巡礼教会ケッペレやシュパイヤー、オッペンハイム、建設中断中のケルン大聖堂も訪問する徒歩旅行をし、ハイデルベルクのボアスレーの中世のドイツ絵画コレクションに感銘を受けた。文献学の道を歩んでいたランケは歴史書に魅了され、手書きの原典史料研究に進むが、1826年『ドイツ中世資料集Monumenta Germaniae Historica』第一巻が出版された翌年から31年まで、MGH編集者ペルツに習い、原史料探求のため5年間、南方(ウィーン、イタリア諸都市)旅行をしている。またこのときペルツに手紙を書き、MGH編集のために弟子ヴァイツを派遣した。最晩年の『世界史』ではMGHを引用、著作の5分の2を中世に割いている。ランケの中世への憧憬には、時代の影響ばかりでなく、青年時代の体験がその根底にあると思われる。
各報告の後、活発な討論が行われました。

足をお運びくださいました方々に、改めて深く御礼申し上げます。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample