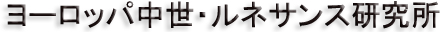ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第八回研究会報告
去る11月5日に早稲田大学にて当研究所の第八回研究会が開催されました。

プログラムは以下の通りです。
全体のテーマ:越境するルネサンス
報告
清水 憲男(早稲田大学文学学術院教授)
「ルネサンス―揺さぶりをかけるスペイン―」
喜多崎 親(成城大学文芸学部教授)
「中世とルネサンスのあわい ― 規範としてのフラ・アンジェリコ」
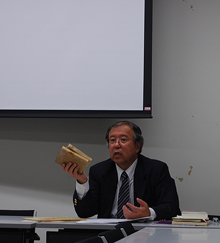
清水氏は、20世紀前半の歴史学や哲学においてはスペインのルネサンスに否定的な見方が根深いながらも、同時期にルネサンスを論が出版されていたことを指摘され、それを皮切りに、スペイン文学におけるルネサンスを包括的に概観された。その萌芽は15世紀半ばに見られ、1492年にはネブリハによる画期的な『言語論』が、16世紀前半にはボスカンとガルシラソらによるカスティリオーネの『廷臣論』の優れたスペイン語翻訳と俗語擁護論が生み出され、ルネサンス成熟期のルイス・デ・レオンの作品に結実する。詩は庶民にも広がり、神秘主義文学や騎士道小説、ピカレスク小説が流行した。学問や歴史と同様に、これらの文学は新世界の植民地征服を背景とした同時代の新しい思想の影響を受けつつも、完全に血肉化して継承された中世や古典古代をはらんでいる。この重層構造にスペインのルネサンスの独創性がうかがえるのである。

喜多崎氏は、19世紀中頃のフランスでに宗教画の規範と目されていたフラ・アンジェリコに関し、評価史を辿り、具体的な作例を挙げながら、どのような点が規範と考えられたのかを紹介された。批評家らの言説とは裏腹に、明らかにフラ・アンジェリコを参照したアモーリ=デュヴァルを除いては、フラ・アンジェリコの名を借りて評された画家らの作品から、直接的な造形上の近似を見出すことは難しい。カトリック復興と宗教画刷新運動のなかで、画家達は、盛期ルネサンス以降の異教的な絵画を避け、キリスト教化された古典的様式を模索するうえで、中世からルネサンスへの過渡期にあるフラ・アンジェリコを象徴的、理念的な規範として称揚したのではないかと結論された。

お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample