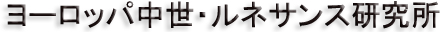ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 国際シンポジウム報告
去る2019年11月10日に早稲田大学において、当研究所の第十回シンポジウムが開催されました。 基盤研究(B)「中近世キリスト教世界における宗教と暴力-対立と和解のポリティクス-」および基盤研究(B)「中近世ヨーロッパにおける「正しい認識力」観念の変遷」との共催の国際シンポジウムでした。
プログラムは以下の通りです。
International Symposium "Religion and Violence in Medieval and Early Modern Europe"
Moderator: Taku MINAGAWA (Univesity of Yamanashi) Foreword
Speakers
1.Arno STROHMEYER(Universitat Salzburg), Religion und Gewaltin denhabsburgischen Erblander; Georg Erasmusvon Tschernembl und sein Traktat "De resistentia subditorum adversus principem legitima"(1600) 13:30-14:05
2.Marco PELLEGRINI (Universitadi Bergamo), Papacy and Holy War from the Middle Age to the Renaissance 14:05-14:40
(break) 14:40-14:50
3.Morihisa ISHIGURO(Kanazawa University), The Violence and Religious Covenantin Machiavelli14:50-15:20
4.Takashi JINNO(Waseda University), Tyrannicide and Religious Justice-The Doctrines of Tyrannicide of John of Salisbury and Juan de Mariana 15:20-15:50
(break)15:50-16:00
Commentator 1 Kuninobu SAKAMOTO(Meiji University) 16:00-16:15
Commentator 2 Tomoji ODORI(Musashi University) 16:15-16:30
Discussion 16:30-17:30


シュトローマイヤー氏は、宗派対立の時代、ハプスブルク君主制への抵抗が、どのような条件のもとで可能だったのか、上オーストリアのプロテスタント亡命貴族によって著されたとされる、『抵抗について』と題した論文を分析することで論じた。人文主義的な歴史思想に基づいて過去の先例を挙げながら著者が強調するのは、支配者と諸身分との間の契約による結合という観念である。ヨーロッパでは君主と臣民との関係が双務的関係を伴う臣従礼によって規定されているゆえに、この国制のもとでは君主の些細な過失に対してではなく、法と慣習に対する酷い侵害、すなわち国制を覆す試みや宗教和議に対する侵害に対してのみ抵抗が許される。抵抗は、請願のような形から脅迫、防衛的行動、君主の助言者に対する暴力のような形へと段階的にエスカレートしなければならない。君主自身に対し物理的暴力を行使することはできないが、限定的廃位や、臣従礼の拒絶による登位阻止は許される。著者によれば抵抗の権利を持つのはあくまで諸身分であり、全階層の臣民が個人として抵抗を行うことは認められていなかった。

ペレグリーニ氏は、15世紀の十字軍思想と16世紀のカトリック君主による「聖戦」との間にある連続と転換の過程を検討した。氏は、「教皇十字軍」は遡行的に創られた観念であり、同時期のオスマン帝国の拡大とキリスト教勢力の劣勢という文脈において成立したとする。ピウス2世は1460年、自ら軍勢を率いて異教徒への遠征を計画したが、この際、従来の「武装巡礼」「渡海」「聖なる業」といった用語に代わって初めて「十字軍」を宣言した。この俗語起源の用語は、贖罪という含意から転じて、聖地遠征のための特別課税、財政的貢献、ローマ教会の要請による世俗君主たちの招集を示唆している。この用語の意識的選択は、ルネサンス教皇による、中世教皇権の「復興」意図に基づいており、具現化した聖戦意識は16世紀にまで引き継がれた。ただし、かつてのグレゴリウス7世を彷彿とさせる教皇直率の軍事遠征、「教皇十字軍」は、結局、ピウス2世以降非現実化し、むしろ16世紀にオスマン帝国への対抗策として促進されたのはウルバヌス2世的な「両剣論」に基づく世俗君主への軍事的差配権の委託、すなわち神聖同盟であった。

石黒氏は、マキァヴェッリの宗教観について論じたが、先行する学者たちの見解は、彼が宗教を政治的効用から捉えていたとみなす見解、逆に彼の宗教性をより強調する見解、異端思想、終末思想の反映をみる見解、キリスト教を社会の発展に有害とみなしていたとする見解、あるいは他宗教との比較でキリスト教を相対化したという見解、のように錯綜し矛盾している。それゆえ氏は、暴力と宗教との関係に限定して議論を進めるべきであるとする。マキァヴェッリは同時代のキリスト教を始原からの逸脱とみなして批判し、「荒廃と罰」からの回復を訴えている。社会の腐敗が極限まで進んだ場合、指導者たちは美徳ではなく、暴力的手段に訴えるほかないが、それは古代ローマや聖書の立法者、預言者たちの在り方と同じであり、神と語らう預言者の言葉も、それを実現する力がなければ失敗に終わるほかない。マキァヴェッリは伝統的な共同体の倫理が崩壊した16世紀のイタリアで、献身と自己犠牲に基づいて新たな契約を結び、強制によってそれを具現化する宗教的指導者あるいは立法者の教育を意図していた、と氏は結論する。

甚野氏は、12世紀の神学者ソールズベリーのジョンと、16世紀のイエズス会士フアン・デ・マリアナの暴君殺害論を比較した。教皇グレゴリウス7世以降、暴君追放は神の正義の回復、一種の聖戦とみなされたが、ジョンは頭と四肢の調和という有機体のメタファーに基づいて王国を論じた。彼は無条件の暴君殺害を認めているわけではなく、すべての権力は神に由来するとし、異教徒の常套手段ゆえに毒殺は認められないなど、厳しい制約を課している。ジョンの議論は近代的な抵抗理論というよりは「両剣論」に基づく世俗権力に対する教会の優越の主張である。マリアナは、会議による忠告など段階を踏んではいるが、同時期のアンリ3世暗殺を称賛した。アンリ4世暗殺後に著作は焚書処分を受けたが、その思想がイエズス会の公式見解とみなされ会士追放の一因ともなった。もっともマリアナの議論は理想の君主と暴君を対置し、慎重さの美徳を称揚するという点で、十字軍時代に生き、テオクラシー理念を前提としていたジョンに対し、カトリック国家スペインの君主を教育するという文脈で語ったマリアナという違いこそあれ、「君主鑑」の系譜として論じるべきである。
 (写真はコメンテーターの踊氏、坂本氏)
(写真はコメンテーターの踊氏、坂本氏)
報告後、会場からの質問を交えたディスカッションが行われました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも記して感謝申し上げます。
お運びくださった皆様、ありがとうございました。
(文責 鈴木)
Designed by CSS.Design Sample