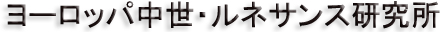ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第十回研究会報告
去る6月30日に早稲田大学にて当研究所の第十回研究会が開催されました。

プログラムは以下の通りです。
それぞれのお名前は報告要旨にリンクしています。
全体のテーマ:「リヴァイヴァル―ヨーロッパ文化における再生と革新」
報告者:
益田朋幸(早稲田大学文学学術院教授)
聖母マリアの予型―ビザンティン美術におけるリヴァイヴァルとサヴァイヴァル―(PDF版)
瀬戸直彦(早稲田大学文学学術院教授)
中世における二つのトポス:『雅歌』と『秘中の秘』(PDF版)

益田氏は、13世紀末から14世紀初めのマケドニアにおける二つの聖堂壁画を例に、聖母マリアの予型、すなわち旧約聖書において聖母マリアの前触れが象徴的に表れるとする予型論の表現を考察された。スタロ・ナゴリチャネおよびオフリドのパナギア・ペリブレプトス両聖堂には同じ制作者による壁画「聖母の眠り」があり、旧約聖書の王や預言者らが聖母の予型のシンボルを伴って描かれている。報告ではパナギア・ペリブレプトス聖堂のナルテクス(玄関廊)の壁画を主に紹介された。ナルテクスの壁面は中央天井の、天使の姿で顕現するキリストを囲むように聖母マリアの予型を表す旧約聖書の諸場面や預言者のシンボルが配されている。ビザンティン世界では聖母マリアの予型論は4世紀に遡り、6世紀のロマノス・メロドスによって体系化された。これらの作例の美術的表現が、イコノクラスムを生き延びて受け継がれていたのか、あるいは古代復興を意図し新たに採用されたのかという点が着目されるのである。
 瀬戸氏は、ガース・ブリュレの作とみなされてきた北仏語の抒情詩と、オック語によるオジル・デ・カダルスの教訓詩を皮切りに、「トポス」の方法論を提示された。現代の読者には脈絡や整合性なく挿入される語句を「トポス」ととらえ、当時の共通した意識的基盤を理解する手法である。両詩には『雅歌』(Ⅲ-1)に基づく定形句が認められ、このことは後世の不必要な修正からも裏付けられる。また『秘中の秘』養生術に関する部分にもトポスの例をみることができる。オック語版とラテン語版の「四季の健康術」における部分と、「食後の胃もたれ」についてのラテン語版と古仏語版を比べると、女性の扱いに関しておどろくべき対処法が紹介されている。背景にはアラビアの百科全書的著作の伝統が影響を与えた可能性が高い。このようにギリシア・ラテンの西欧古典の伝統以外にも8世紀以降のイスラムの伝統がトポスとして見出されるのである。
瀬戸氏は、ガース・ブリュレの作とみなされてきた北仏語の抒情詩と、オック語によるオジル・デ・カダルスの教訓詩を皮切りに、「トポス」の方法論を提示された。現代の読者には脈絡や整合性なく挿入される語句を「トポス」ととらえ、当時の共通した意識的基盤を理解する手法である。両詩には『雅歌』(Ⅲ-1)に基づく定形句が認められ、このことは後世の不必要な修正からも裏付けられる。また『秘中の秘』養生術に関する部分にもトポスの例をみることができる。オック語版とラテン語版の「四季の健康術」における部分と、「食後の胃もたれ」についてのラテン語版と古仏語版を比べると、女性の扱いに関しておどろくべき対処法が紹介されている。背景にはアラビアの百科全書的著作の伝統が影響を与えた可能性が高い。このようにギリシア・ラテンの西欧古典の伝統以外にも8世紀以降のイスラムの伝統がトポスとして見出されるのである。
お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample