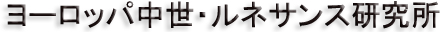ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第十三回研究会報告
去る6月29日(土)に当研究所の第十三回研究会が開催されました。
今回は早稲田大学高等研究所(比較文明史エリア)との共催になりました。
プログラムは以下の通りです。
それぞれの報告者のお名前は要旨記事にリンクしています。

司会:益田朋幸(早稲田大学文学学術院教授)
報告者:
坂田奈々絵 (日本学術振興会特別研究、上智大学) (PDF版)
「12世紀のサンドニ修道院における擬ディオニシオス文書の伝統」
久米 順子(東京外国語大学講師)(PDF版)
「キリスト教美術とイスラーム美術が交差するところ:中世スペインの場合」
坂田氏は、12世紀にサン・ドニ修道院の修道院長を勤めたシュジェールと5世紀の擬ディオニュシオス文書、ローマ帝政期にガリアに派遣され殉教した聖ドニとの関連性の問題を、同聖堂に残された碑文(1140、1144)や『献堂記』などの一次資料から精査された。擬ディオニシウス文書の影響を受けたシュジェールをゴシック建築様式の祖とするパノフスキーの著名な説は、その光の形而上学の神学理論と建築との関係性が不明であるため1980年代以降批判を受ける一方で、シュジェールと擬ディオニュシオスの関係性については再検討もなされている。そこで発表者は、サンドニ修道院における聖ドニ崇敬に着目した。サン・ドニ修道院が成立する7世紀以降、パリで殉教した聖ドニとアテネのディオニュシオスは同一視され、12世紀当時にはその伝統が確立していた。ラテン世界に現存した擬デュオニシオス文書は9世紀の修道院長ヒルドゥインにより翻訳、注解が作られ、同時代のエリウゲナによる再注解も残されている。その中で、擬ディオニュシオス文書は聖ドニの著作として考えられ、聖ドニを讃える賛歌のうちにも、擬ディオニュシオス文書に特徴的な概念が様々に登場する。発表者はそこに見出される「光」という用語が、擬ディオニュシオス文書の概念を踏襲しながらも、古典的なラテン世界の賛歌における「光」の使用に結び付けられているという点を指摘した。そしてこうした傾向はシュジェールの碑文における「光」という言葉の使用に共通した特徴がある、という点を示唆し、デュオニシオスの光の思想は聖ドニへの崇敬の念とともに受け継がれていったと結論された。

久米氏は中世のイベリア半島においてキリスト教とイスラームと教との接点を工芸、聖遺物、織物、建築などから多角的に取り上げ、最近の研究と豊富な現地資料を紹介された。半島南部のイスラームの支配地域アル・アンダルスが繁栄を見せた10世紀から、北部のキリスト教諸王国がレコンキスタ運動を進展させる13世紀を中心に作例を見た。著名なベアトゥス写本にはイスラームの建築などを描いたモティーフやクーフィック文字による装飾などが残るが、これはイスラーム治下のキリスト教徒モサラベが北部キリスト教国に再入植したものないしそれらを反映したものと考えられる。このほか、たとえば13世紀の北部ラス・ウェルガス修道院に保存されているイスラー ムの刺繍入り軍旗など戦利品として奪った品もあれば、クリスタルやカットグラス、象牙細工、多量の織物や陶器など、イスラーム諸国からキリスト教国への贈答品だったものもある。イスラームの精巧な工芸品はキリスト教の修道院の宝物や聖遺物入れに転用されるなど、異文化の美術品が珍重される下地があったことがうかがえる。また、キリスト教支配下のムスリムたちによるムデハルの美術も紹介し、とくに石材ではなく煉瓦と木材を使用するムデハル建築はロマネスクやゴシック、ルネサンスの各様式と融合して広く発展したことを指摘された。また、トレドのキリスト教教会に改装されたモスクなどのアラビア文字装飾や、アラビア文字でつづられた外国語アルハミアなど語学の相互浸透の問題にも触れた。二つの美術の関わりの複雑な背景と多様性、そして今後の研究への問題点も提示された。

お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample