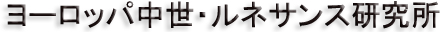ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第十八回研究会報告
去る4月18日(土)に早稲田大学において当研究所の第十八回研究会が開催されました。
 高等研究所セミナーシリーズ【研究エリア〈新しい世界史像の可能性〉】との共催でした。
高等研究所セミナーシリーズ【研究エリア〈新しい世界史像の可能性〉】との共催でした。プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
()内からはPDF版の要旨記事にリンクを張っております。
各要旨のテキスト版はこちらになります。
「トルヴェールの作品校訂に関する問題:ペラン・ダンジクールの例(13世紀半ば)」(PDF版)
佐藤ヴェスィエール吾郎(パリ第4大学大学院博士課程)
「「調和をもたらす王」と音楽の隠喩――リチャード2世治下のイングランドにおける君主鑑と王権」(PDF版)
武田啓佑(早稲田大学大学院博士課程)
「エックハルト思想における<中間のもの>(medium)概念と<離脱>」(PDF版)
若松功一郎(早稲田大学大学院博士課程)

佐藤氏は13世紀半ばのトルヴェールの作品が収録された写本群から、ペラン・ダンジクールの作品を軸に、新たな本文校訂を試みる研究を紹介された。先行研究とその方法論の問題点を、具体的な作品と写本のテキストを挙げて詳細に検討し、そのうえで特定の写本を底本に選択した経緯と独自の校訂例を明らかにされた。

武田氏は中世後期イングランドの王権と音楽との思想的・政治的な関連性を、リチャード2世とジョン・ガワー(1330?-1408)の著作を中心に詳細に検討された。ガワ―の作品においては世界の調和と音楽が結び付けられ、音楽家のように王国を調和させる古代的な理想王が描かれるが、一方で君主鑑的な伝統と、国王自身の王権概念・実践的な音楽利用との間に隔たりが存在することも明らかになった。

若松氏は14世紀初頭の神学者エックハルトのドイツ語著作において語られる「離脱」の教説をラテン語著作から分析された。「離脱」では神の意に叶うために人間がとるあらゆる手段が棄却されるが、この手段はラテン語著作における中間のもの(medium)に相当し、エックハルトが神と人との関係を三位一体の父と子になぞらえるために媒介的なものは否定されるという論理的基盤を指摘された。

盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。 お運びくださった皆様、ありがとうございました。
(文責:鈴木、毛塚)
Designed by CSS.Design Sample