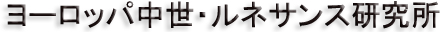ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第七回研究会報告
去る7月16日、「ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所」第七回研究会が 早稲田大学にて開催されました。 全体のテーマは「中世の時間意識」でした。 プログラムは以下のとおりです。
報告:
黒田祐我(早稲田大学文学学術院助手)
「複合的な暦と時間意識 -『辺境』としての中世イベリア半島-」(PDF版)
櫻井 夕里子(早稲田大学文学学術院非常勤講師)
「アナスタシス(キリストの冥府降下)図像に内在する時間」(PDF版)

黒田氏は、中世イベリア半島独自の西暦より38年早いイスパニア暦の起源と使用状況を具体的な史料をもとに紹介された。ヒスパニア暦は、カスティーリャやポルトガルにおいて14世紀末まで広く用いられていたのに対し、カタルーニャ諸伯領では11世紀の段階でほぼ西暦が使われ、ナバーラやアラゴンでは13世紀前半には利用が減るなど、地域的な差異は大きい。また、11世紀以降、アンダルスとの交渉が盛んになるにつれ、ヒスパニア暦とヒジュラ暦が併記されるようになる、など地理的、国家的にも辺境にあったイベリア半島ならではの重層的な時間意識が伺われた。

櫻井氏は、8世紀頃より現存するアナスタシス(キリストの冥府降下)図像を紹介したのち、当図像の主要な登場人物である旧約聖書の王ダビデとソロモンについて考察した。エルサレムに神殿を奉献したことで名高いソロモンは、エルサレムに聖墳墓聖堂を献堂したコンスタンティヌス大帝に重ね合わされる修辞学的伝統を持つ。なかでも、11世紀中頃のキオス島、ネア・モニ修道院の作例では、常ならば若者で描かれるソロモンが有髯の老人で描かれ、当修道院の寄進者と目されるコンスタンティノス9世モノマコス(在位1042-55年)の容貌が当てられていると考えられている。エルサレムに神殿を築いたソロモンと聖墳墓聖堂を献堂したコンスタンティヌス大帝が合わせて称えられたことを考えるならば、聖墳墓聖堂を修繕し、多くの聖堂を立てたモノマコスもこの系譜に自らを連ねたのである。アナスタシス図像の中に、キリストの死と復活、旧約の預言者、4世紀そして同時代といった複数の時間が内在する一例である。
暑いなか、お運びくださった皆様、ありがとうございました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample