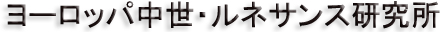ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第十九回研究会報告
去る6月27日(土)に早稲田大学において当研究所の第十九回研究会が開催されました。

高等研究所セミナーシリーズ【研究エリア〈新しい世界史像の可能性〉】との共催でした。
プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
お名前からはテキスト記事、()内からはPDF版の要旨記事にリンクを張っております。
第十九回研究会
日時:2015年6月27日(土)14時~17時半
場所:早稲田大学戸山キャンパス39号館2階2219教室(美術史実習室)
報告:
「「復古」と「一なる教会・一なるキリスト」:12世紀キリキア・アルメニアにおける教会合同をめぐる言説と歴史意識」(PDF版) 浜田華練(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)
「アヴィニョン・ナポリ・プラハの宮廷写本(1320-70年頃)―国際的ゴシック様式の形成に関する寄与―」(PDF版) 大野松彦(東京藝術大学大学院専門研究員)

浜田氏は12世紀後半のアルメニア教会とビザンツ帝国との教会合同交渉において、伝統的なキリスト論がどのように提示されたかという点をアルメニア語、ギリシア語などの各史料を挙げながら詳細に分析された。アルメニア教会の指導者ネルセス・シュノルハリが独自に発展を見せたキリストの神性と人性を合一を教会合同を推進する教義的な根拠として敷衍させたことを明らかにされた。

大野氏は14世紀の装飾写本における国際ゴシック様式の広がりと発展について、アヴィニョン、ナポリ、プラハの各宮廷工房で制作された作例を比較され、詳細に検証された。とくに近年の研究で着目されるアヴィニョンの画家とその挿絵様式は、各地の様式が混交する先駆けとなり、ナポリとプラハとに影響を相互に与え合い続け、王侯貴族や聖職者の庇護と作品や作家の交流に伴って高度に洗練されていくという流れを提示された。

盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも付して感謝申し上げます。
お運びくださった皆様、ありがとうございました。
(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample