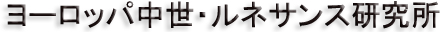ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所 第八回シンポジウム報告
去る2017年9月30日(土)に早稲田大学において、当研究所の第八回シンポジウムが開催されました。 「早稲田大学高等研究所セミナーシリーズ〈新しい世界史像の可能性〉」との共催でした。

プログラムおよび報告要旨は以下の通りです。
お名前隣のPDF版のテキストリンクに要旨記事を掲載しております。
共通のテーマ「宗教改革期の図像」
報告1
高津 秀之(東京経済大学経済学部専任講師)報告要旨(pdf)
「100年後の「アウクスブルクの信仰告白」―1630年の宗教改革のプロパガンダ―」
報告2
冬木 ひろみ(早稲田大学文学学術院教授) 報告要旨(pdf)
「16世紀後半から17世紀のイギリスにおける宗教とエンブレムの関係」
報告3
松原 典子(上智大学外国語学部教授)報告要旨(pdf)
「対抗宗教改革期のスペインにおける宗教図像
―宮廷説教師パラビシーノと宗教画における裸体描写をめぐって―」

高津氏は、1530年アウクスブルク信仰告白から100年を記念し、1630年にドイツを中心に出版されたビラの挿絵を詳細に分析された。ビラの版画は、皇帝カール五世が信仰告白する場面などを描き、プロテスタントとカトリックの併存体制を保護する穏健な内容と、プロテスタントを擁するスウェーデン王グスタフ・アドルフがカトリック側に対峙する騎士として描かれるなど戦いのイメージが強調される内容とに細かく分けられることを指摘された。

冬木氏は、16世紀後半から17世紀のイギリスで出版されたエンブレムを分析され、宗教的な図像と世俗的な図像の割合、文字部分の重要性を検討された。エンブレムには、伝統的なキリスト教図像、プロテスタント側の反カトリックの図像、ジェイムズ1世の王権を称揚したもの、さらには同時代のイエズス会からの絵画的イメージなど多岐にわたる影響関係が反映されている。これらのイメージは同時代の詩や劇でも言及され、イギリスにおける図像と言葉と結びつきの強さが改めて指摘された。

松原氏は、16世紀後半からの対抗宗教改革期スペインの美術、とりわけ宗教画の禁欲性に関して、1563年のトリエント公会議で決定された「聖像に関する教令」とその影響を、関連史料を多数挙げながら詳細に検討された。なかでも、厳格な説教で知られる宮廷説教師パラビシーノ(1580-1633)の聖像の裸体描写に対する批判的な言説と、王室や貴族らの絵画コレクションの裸体描写に対する見方が道徳的側面から厳格化された時期が符合することから、両者の関連性や共通の背景の存在の可能性をを指摘された。
報告後、会場からの質問を交えたディスカッションが行われました。
盛況であり、また活発な質疑応答がなされたことも記して感謝申し上げます。
お運びくださった皆様、ありがとうございました。

(文責:毛塚)
Designed by CSS.Design Sample